青銅器時代

https://www.researchgate.net/figure/The-four-bronze-swords-examined_fig1_235790046
使われていた期間=紀元前3300–紀元後1200
人類が銅にはじめて出会ったのは紀元前8000年頃の新石器時代で、錫は紀元前5000年ごろで、あわせて青銅として本格的につかいだしたのが紀元前3500年頃であるとされています。
銅は非常に柔らかい金属なので、実際には、銅と錫(英語でTin)の合金である青銅にして使われています。
銅像は英語でブロンズ像Bronze figures 現代で使われている場面は、十円玉や銅板ぶきの屋根や、あま樋などです。オリンピックの銅メダルも表面は青銅=ブロンズです。。
ちなみに「ハンダづけ」のハンダは、錫(スズ、Sn)と鉛(なまり、Pb)が約6:4の比で混ざってできた合金です。200℃程で溶けるので使われています。
銅copperにスズtinをまぜたのが青銅 青銅=ブロンズbronzeです。
copper + tin = bronze です。
元素記号は 銅Cu 錫スズ Sn
銅の融点は 1084.5 です。
スズ(錫)Sn の融点は 231.96 です。
比較的、低温で溶けるから、人類史のはじめのほうで使われるようになったんですね。
ちなみに、鉄Fe の融点は 1536 です。500度高いですね。
鉄器時代
紀元前1200から
鉄器時代の開始は定説では紀元前1200ごろからヒッタイト帝国(現代のトルコ)ではじまった。
鉄はその当時のスーパー最先端技術
最初は砂鉄をあつめて、たたらで鉄を作った。たたら=ふいごの事。
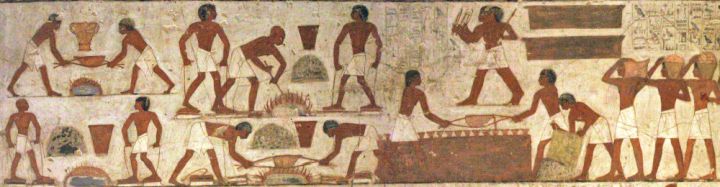
鉄の生成。砂鉄 砂鉄の主成分は酸化鉄。いわゆる黒錆び。
粘土製の炉で、木炭の火で加熱した。
足でふいごを踏んで炉に風を送って炉熱の温度を高めた。
一酸化炭素が酸化鉄につく→→ 二酸化炭素になって、鉄から酸素を奪って離れる。 海綿状の金属鉄が残る。この化学反応に必要な温度は400から800度ほど。そのあと、熱せられた鉄を叩いてギュっとさせる。
日本の昔の製鉄は、鉄を1536度まで熱してドロドロに溶かして製品にしてたわけじゃない。低温で比較的柔らかくしたらあとは、ガンガン叩いて形にしていた。その叩く過程で不純物が除去されて、
さらに炭に包んでガンガン叩いて炭素分を加えた。それで炭素と鉄の鋼になった。
次の時代になると鉄鉱石を山からとって炉で熱した。
日本は、弥生時代の間に、大陸から青銅と鉄器が一緒につたわって、石器時代からいきなり鉄器時代になりました。
鉄と鋼の違いは
「鉄と鋼ってなにが違うのでしょう?」鋼とはなんでしょう。
鋼とは=鉄と炭素が混ぜ合わせられたものが鋼です。鋼は、鉄に0.02%~1.7%の炭素を加えた合金のことです。
鉄(Fe)と炭素(C)の合金です。ぜんぶのFeがCとくっつくわけではないので、FeCではないです。
Cがゼロだと、純粋な鉄(Fe)です。
Cが入っているものが鋼
FeにCが混ざる割合で、鉄、鋼、鋳鉄の区別ができるのです。
いま一般的に日常生活で身の回りで”鉄”って呼ばれているものはすべて鋼です。わざわざ「これは鋼です」。って言わないだけで、鉄筋コンクリートとか、鉄骨とよばれるものは鋼です。
英語だと、鉄がIRON(アイアン)。鋼がSTEEL(スティール)です。
炭素が入っていればいるほど固くなります。
純粋な鉄は軟らかい
↓
鋼がちょうど手頃な硬さと可塑性がある(曲げたりして加工できる)
↓
鋳鉄は炭素が多すぎて脆くなる
鋼
鋼は鉄Feよりも強度と靭性(粘り強さ)、加工性に優れる、武器などに利用される。
C=0.04~2.1%、つまり0.04/100~2.1/100(重量)
軟らかいFeにCがわずか0.04~2.1%入っただけで硬い鋼に変身する
高温で溶かした鉄を、砂などで作った型の空洞部分に流し込み、冷やして固めた製品を「鋳物(いもの)」と言います。鋳物をつくることが「鋳造(ちゅうぞう)」です。
炭素が多すぎるくらいに入っているものが鋳物(鋳鉄)です。鉄瓶とかがそうです。
刀の作り方
現在は、全国にいる刀匠は約250名のみ 2017年で188人?
刀は鋼。刀の炭素の含有量は1~1.5%程度。
鉄の融点は1535℃だけど、刀は木炭で加熱してるから、1000度から1500度で加熱。完全にどろどろにならないで、柔らかい個体の状態で加工する。
たたら製鉄
「鉄滓(のろ)」ガラスなどの不純物を含むスポンジ状の海綿鉄。たたらからドロドロっと出てくるやつ
「鉧押し(けらおし)」砂鉄から直に鋼を作りだす直接製鋼法
鉧(けら) たたら炉を壊して下にたまった鉄、なかに成分として玉鋼を含む
銑(ずく)は、鉧の中に含まれている低品質な鉄。:炭素約2.1%以上を含有。鉄瓶などの鋳物は4パーセントほどの炭素含有量。
鉧から鑑別される良質の鋼「王鋼」は約1/3~1/2
鉧 (けら。粗鋼の塊) の中に3分の2程度含まれる玉鋼
玉鋼1級品 炭素を1.0 – 1.5%含有し、破面が均質なもの。
玉鋼2級品 炭素を0.5 – 1.2%含有し、破面がやや均質なもの。
玉鋼3級品 炭素を0.2 – 1.0%含有し、破面が粗野なもの。
玉鋼1kgあたりおおよそ文化包丁1本分
砂鉄は燃え上がる炭のすき間を落下する間に還元と呼ばれる化学変化を受けて鉄に変わる。
砂鉄から玉鋼は 1.5 割くらい 10トンで1トン~2トンくらい
鉧から玉鋼1級品に当たる部分は約2割程度
日本刀を作るには7,8キロの玉鋼が必要
玉鋼は6-4kg から 1kgの刀になる。20%くらいがのこる
玉鋼は5000円/kg
打刀は 研いで完成時点で 800g~900g くらい
繰り返し鍛錬
「王鋼」はわずかに含まれる不純物が折り返し鍛練によって微細化・分散化することで、刃物鋼に求められる粘り強さ、研ぎ性といった性質をかえって向上させている
叩いては伸ばし、2つ折りに折り曲げて、叩いては伸ばし、2つ折りに折り曲げて・・の作業を15回ほど繰リ返す。「折り返し鍛錬」炭素量を減少
繰り返し鍛錬すると次第に炭素量が下っていき、仕上がり時は0.7パーセント前後の炭素量
1回折り曲げて2層。で2倍を15回すると、32,768枚の層になる。
2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768 の式
16回 折り返して65536の層にしなかったのは、3万の層の方が使い勝手がよかったんだろうね。
炭素量が減りすぎるからか?炭素量が減るとやわらかくなる
炭素量が多くすればするほど、硬度が増し固くなる。しかし、折れやすさがあがる。粘りがない
炭素量を少なくすればするほど、硬度は減りやわらかくなる 折れにくくなる。粘りがある

画像引用元
折り返し鍛錬でできた
炭素量の多い硬い鋼(皮鉄:かわがね)
炭素量の少ないやわらかい鋼(心鉄:しんがね)
炭素量が多いと皮鉄を外見に使って外側を硬くして、炭素量が少なくてやわらかい心鉄を芯につかって中身をやわらかくする。